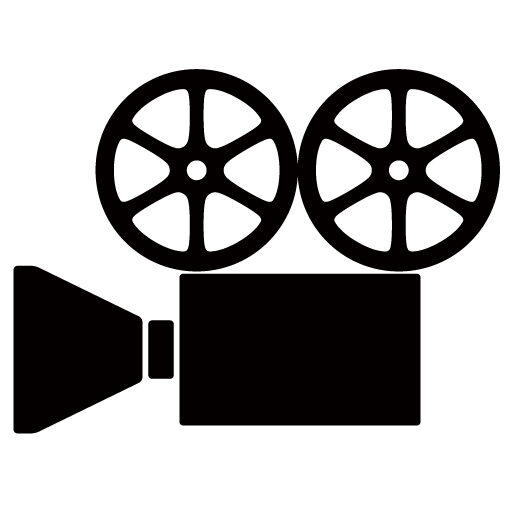講演会
「俺のゴダール」
・講師:四方田犬彦
2022年12月13日 総人棟1B05(16:45-18:15)
報告:中村洸太
映画監督ジャン=リュック・ゴダールの死から3ヶ月後の12月13日、映画メディア合同研究室では四方田犬彦氏をお招きし、講演会「俺のゴダール」を開催した。前日にICA京都にて「パゾリーニのすべて アビューラ(異端誓絶)」という題目で講演をされていたが、本研究室では四方田氏の希望でゴダール映画を語っていただいた。講演会には学内外から多くの参加者が集い、会場は満員となった。
講演会ではまず、中学生時代にゴダールの『勝手にしやがれ』(1960年)を観て渡哲也主演の『紅の流れ星』の盗作だと思ったという笑い話から、今日まで日活アクション映画をはじめとする世界各国の映画にゴダール作品が与えてきた影響、「遍在するゴダール」が語られた。続いてゴダールの作風の変遷を俯瞰し、ゴダールはパブロ・ピカソと同様に、作品を評価されてはそれを捨てて新たな創造に向かうという、自作に「飽きることのできる才能」を持った作家だったことを強調する。さらにそうした作風の変化は、大島渚がかつて述べたように「女房に逃げられるという一種の才能」[i]と同義であったという。
さらに四方田氏は「映画という表象システムがゴダールという存在を所有しえた」ことは幸運なことであったと主張する。ジョン・ケージが音楽に、マルセル・デュシャンが美術に対して行ったようなメタテクスト的な批評それ自体を作品化するという行為は、映画というシステムのなかでは不可能であり必要でもなかった。一方ゴダールの映画には、高度な批評性に加えて、現前する世界に向き合い、感応し、それを「具体的に表象するということの喜び」に溢れており、そうしたテクストの持つ美しさこそが作品を「映画」たらしめていたのだと四方田氏は強調した。
講演会では、続いてゴダールが80年代から90年代初めに日本のレナウンとフランスのマリテ+フランソワ・ジルボーのために制作したコマーシャル・フィルム(CF)を鑑賞し、そこで見られるゴダール的テーマが検討された。上映されたのは1984年に日本で製作された『勝手にしやがれ』を彷彿とさせるレナウンのCF、80年代ゴダールを象徴する冬のノルマンディーの海岸というロケーションのなかで『気狂いピエロ』(1965年)が模倣される「Closed」(1987-1988年)、『ゴダールの映画史』(1988-1998年)制作中に作られた「Métamorphojean」(1990年)、動く身体が連鎖的にモンタージュされる短編『On s’est tous défilé(全員が練り歩いた)』(1987年)の4作品である。最後の『On s’est tous défilé』については、時間の恣意的操作によって映画で表象されるイメージの政治性を暴く作品の自己言及性が、「行進する/逃げ出す」という相反する2つの意味を持つ「défilé」という単語に象徴されていることが言及された。この13分間の映画にはゴダール作品を貫くテーマが凝集されており、トム・ガニングやジル・ドゥルーズの「運動」への関心とも軌を一にするものだと四方田氏は指摘する。
ゴダールという作家を単に追悼するのではなく、現在進行形でゴダールを発見し続けていくことの展望へと目を向けさせるような、刺激的な示唆に富む講演会であった。
[i]大島渚「解体と噴出—ゴダール」四方田犬彦/平沢剛編『大島渚著作集 第四巻—敵たちよ、同志たちよ』、現代思潮新社、2009年、142頁。